こんにちは😊
現在1歳になる息子を育てる全盲ママです。
今回は、出産後に利用した産後ケア施設(助産院)での生活と、
赤ちゃんのお世話で工夫したことをまとめます。
退院後すぐに産後ケア施設へ
私はパートナーの転勤により実家から離れて暮らしていたため、里帰り出産は選びませんでした。
実家に帰っても日中は家族が仕事で不在となり、結局ひとりで過ごすことになるからです。
地域の保健師さんのサポートで、退院当日から1週間、助産院の産後ケア施設を利用しました。

私は保健師さんが手続きをサポートしてくださったおかげで、スムーズに入所することができました。利用を検討されている方は、早めに地域の保健師さんに相談してみることをおすすめします。
助産院での生活リズム
助産院では、動線に配慮してトイレやお風呂が近い部屋を用意してもらい、安心して過ごすことができました。
お風呂の時間だけ赤ちゃんを預け、それ以外は基本的に自分でお世話。
助産師さんが定期的に様子を見に来てくださり、ナースコールを押せばすぐ来てもらえる環境でした。
食事は毎回とても美味しく、ボリュームも十分。
母乳寄りの混合栄養を考えていたので、しっかり食べて体力を回復することができました。
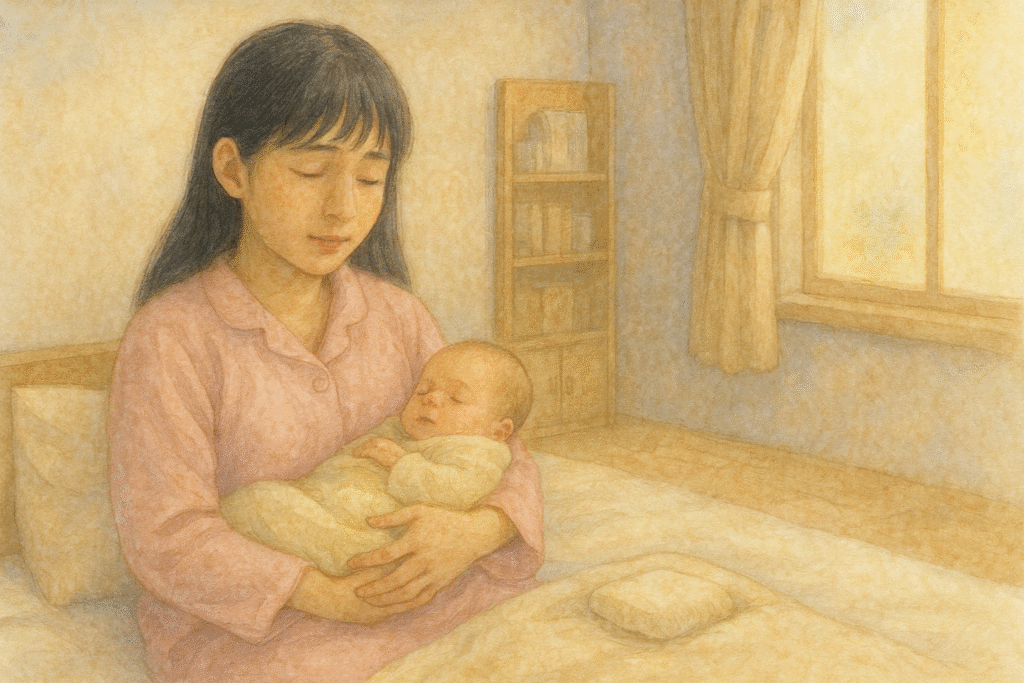
ミルクやおむつ替えの工夫
授乳後のミルクは、助産師さんと相談して
「1日分を作り置き→冷蔵保存→使うときに電子レンジで温める」方法に。
赤ちゃんが飲み終えたかどうかは、
「ごくごく」という飲む音や、哺乳瓶から空気を吸う音を注意深く聞き分けて判断しました。
おむつ替えでは、手順を自分なりにルール化。
おむつ替えシートを敷く → おしりふきを数枚出しておく → 両足を持ち上げて右・左・中央の順に拭く → 最後に仕上げ拭き。
うんちをしたかどうかは、触った感触やにおいの変化で判断し、不安なときは指で確かめることもありました。
こうして「自分なりの確認方法」を持つことで、不安が減り、安心してお世話ができるようになりました。

用意してよかったもの
一番役立ったのは、赤ちゃんの無呼吸を検知してアラームで知らせてくれるセンサー。
助産院でも同じものを使っており、滞在中と退院後に実際にアラームが鳴ったことがありました。
すぐに抱き起こすと、赤ちゃんがぼんやりしていたこともあり本当に怖かったですが、
このセンサーがあったおかげで、安心して眠ることができました。
まとめ
産後ケア施設で過ごした1週間は、私にとって「母親としての一歩」を踏み出す貴重な時間でした。
においや感触、音など五感を頼りに赤ちゃんをお世話しながら、
助産師さんの支えを受けて自信を持てるようになりました。
次回は、いよいよ自宅での新生児との生活についてお話しします。
また次の記事でお会いしましょう(#^.^#)
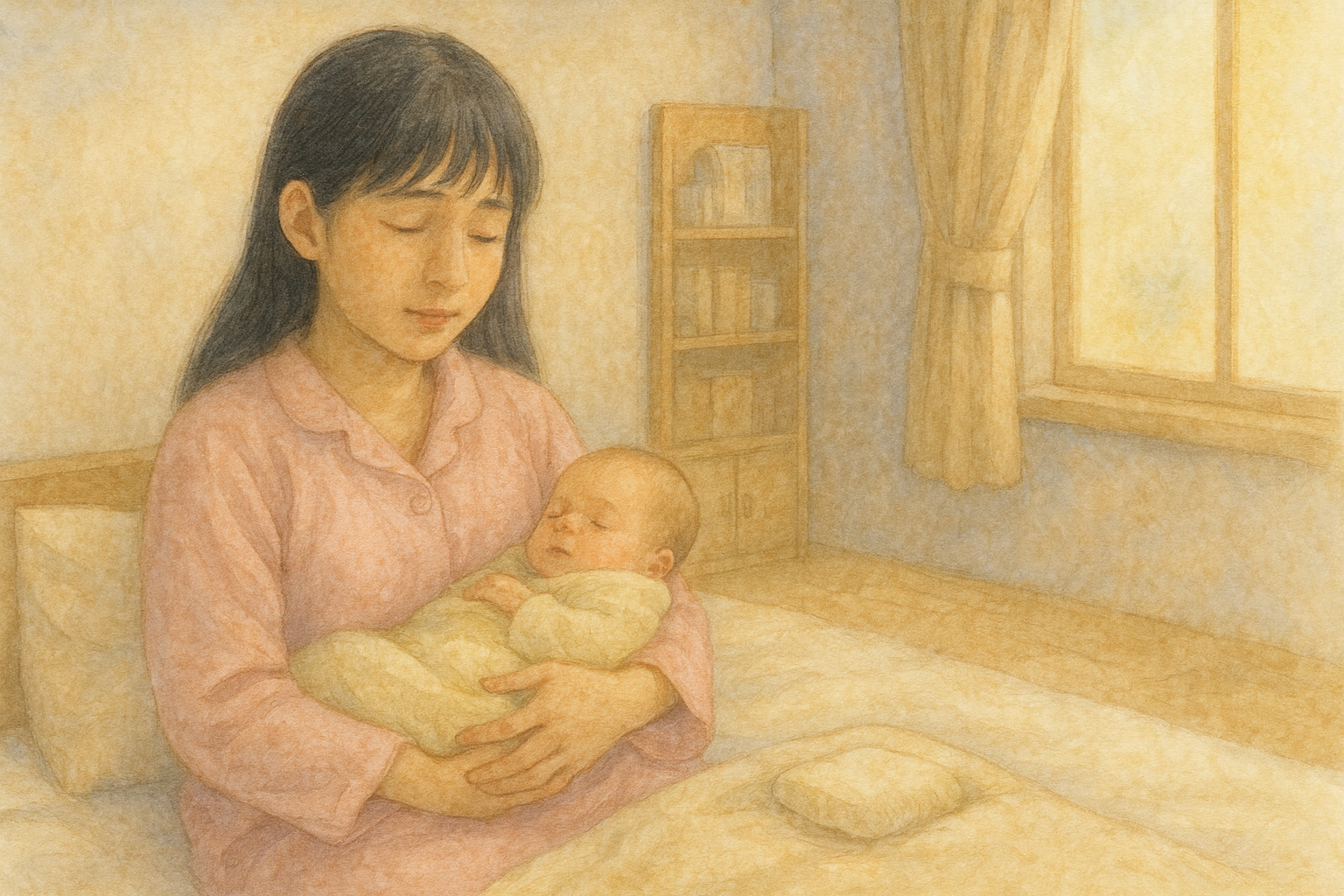


コメント